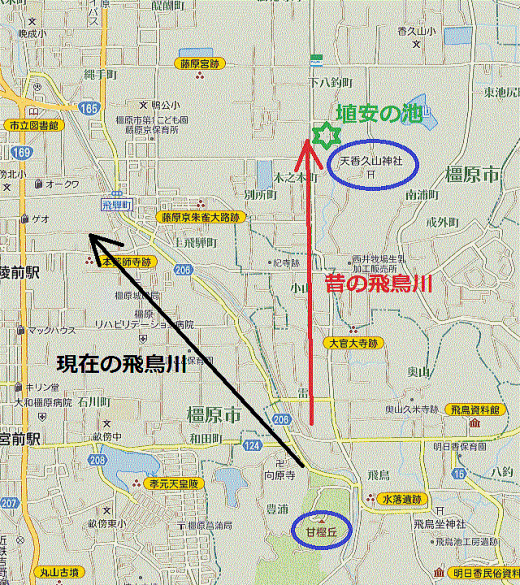| 奈良県の万葉故地への訪問には「大和万葉旅行」(講談社学術文庫)を参考にしている。 それによると、万葉時代には天香具山の西麓にある畝尾都多本神社(哭沢の杜)の北側に「埴安の池」があり、それはとても広大な池であったという。 とりあえず行ってみた。 同書では、「畝尾都多本神社(哭沢の杜)は埴安の池頭の杜で、埴安の水霊をまつったもの」と説明されていたので、まず畝尾都多本神社へ行き、そこから北を見てみた。 それがこれ  池は埋まっており、集落と畑になっていた。  これも。一般的な田舎の風景。 万葉集ではこんなかんじで詠まれている。 |
| 埴安の池の堤の隠沼(こもりぬ)の行方を知らに舎人(とねり)はまとふ | 万葉集 | |
| (私訳) 埴安の池の堤がふさがっているように、 (高市皇子が死んで】舎人達が途方に暮れてる。 |
||
| 白妙の麻の衣き埴安の御門の原にあかねさす日のくれぬるやらん | 万葉集 | |
山部宿祢赤人、故大政大臣藤原の家の山池をよめる
| いにしへの古き堤は年ふかみ 池のなぎさに水草生にけり | 万葉集 | |
| 「大和万葉旅行」によると、埴安の池が地上から消えてしまったのは、池の水を供給していたとされる飛鳥川の流路が変わったためとの仮説を立てている。平安時代の洪水が原因としている。 それによると、飛鳥川は甘樫の丘からそのまま北へ流れ、天香具山の西麓を流れていたという。 多分、この道に沿って旧飛鳥川が流れていたのだろう。  埴安の池から南を向いて写す。 「きのふの淵ぞけふはせになる」と詠われた飛鳥川なので、太古からの歴史の中では、流路の変更もあったのだろう。 |