高野山は、私の自宅から約50キロの距離にある。町全体を真言宗総本山の金剛峯寺の境内とする典型的な宗教都市。世界遺産にも登録され、なにかと魅力的なエリアなのだが・・・ 実は高野山に訪問するのは小学校5年の林間学校以来のこと。この林間学校の時の印象が悪く、自宅から近いにもかかわらず、高野山に苦手意識があった。 林間学校では、夜に 泊まった宿坊で食べた精進料理が口に合わなかったのだ。 育ち盛りの子供にとって、肉の入ってない、山菜とか胡麻豆腐主体の料理は本当に苦痛だった。 多分、この精進料理がトラウマとなって、大人になってからも高野山には足が向かなかったのだと思う。今となっては、50歳を過ぎた中高年になってみると、肉料理よりも、山菜料理の方が十分に魅力的である。 当初、真言密教の道場として、弘法大師が嵯峨天皇から高野山の地を賜ったのが816年。以来、高野山は全山を挙げて宗教活動に専心してきたわけであるが、心ある(?)人はそのような中でも歌を詠み残している。 高野山関連の歌を紹介していく。 |
| たかの山結ぶ庵に袖朽ちて苔の下にぞ有明の月 | 弘法大師 |
| 暁を高野の山に待つほどや苔のしたにも有明の月 | 寂蓮 |
| 今こそは高野の峯の月を見て 深き |
源具親 |
| いかばかり高野の奥のしぐるらむ 都は雲のはるるまもなし | 宗尊親王(続拾遺和歌集) | |
| 高野は「たかの」と読む. 月関連の歌が多い。 次の西行と西住の相聞歌も月関連。かつて奥の院の橋の上で二人で眺めた月を思い出し、西行のいる高野山と京の西住の間で歌の往来がされたもの。 |
| こととなく君恋ひわたる橋の上にあらそふ物は月の影のみ | 西行 |
返し
| 思ひやる心は見えで橋の上にあらそひけりな月の影のみ | 西住 |
*********
| 次は、あまりにも有名なこの歌。 弘法大師は死んでおらず、岩陰から私たちを見守ってくれているという意味。天台宗の延暦寺座主の慈鎮和尚の作。 |
| ありがたや 高野の山の岩かげに 大師はいまだ おわしますなる | 慈鎮 |

奥の院に続く道に歌碑(右側)

頌徳殿(御休憩所)にあった扁額
| この頃、各宗派の高徳な僧侶は、死んだ後も実は生きていて、世界に光明を照らしていると考えられていたようだ。 |
| 大師の住所はどこどこぞ 伝教慈覚は比叡の山 横川の御廟とか 智証大師は三井寺にな 弘法大師は高野の御山にまだおはします |
梁塵秘抄 | |
*********
| 西行は幾度となく高野山に籠って修行を行った。 西行手植えの桜が残る。 |
| 散る花の |
西行 |

西行桜
*********
| 西行桜のとなりにあるのが三昧堂。 修行三昧、念仏三昧など、僧侶が精神を集中させる場所らしい。 与謝野晶子と鉄幹の歌 |
| いにしへの三昧堂をくぐりきぬ 法の御山の星の明かりに | 与謝野晶子 |
| 板しきの冷たきにゐて朝きくは 金剛峯寺の山内の蝉 | 与謝野鉄幹 |

三昧堂の傍らに二首の歌碑
*********
| 父母の しきりに恋し 雉子の声 | 松尾芭蕉 |

奥の院手前に句碑
| 行基が吉野山で詠んだ「山鳥のほろほろと鳴く声聞けば父かとぞ思ふ母かとぞ思ふ」(玉葉和歌集)をふまえている。 |
*********
| 空海の創建以来、高野山は1000年以上女人禁制であった。 高野山の入り口には女性のための籠り堂として女人堂が建てられた。  不動坂口女人堂 |
| さはりある花の名たてか |
花山院師兼 | |
| 白河七百首 | ||
| 罪ふかき名にはたてれど女郎花女人堂をも踏越えて咲く | 唐衣橘洲 | |
| 日南の珠の霰や女人堂 | 桂子 | |
| 原松 | ||
さて、実は高野山という山はない。 標高800メートルにある盆地に宗教施設があり、その周囲を1000メートル級の山々に囲繞された独特の地形である。 冬は寒く雪も積もる。一方、夏はさわやかな気候とのこと。 2022年夏、いったん終息していた新型コロナウイルスが急激に感染が再拡大し、感染第七波が到来した。 そんな中、近場で手頃な観光ができる場所として高野山に行くことにした。小学生以来の訪問である。 奥の院の駐車場に車を停めて、根本大塔までバスで引き返し、奥の院に向かって歩いて行くというプラン。 【現地訪問】  三鈷松 弘法大師が唐の国から投げた三鈷がこの松に止まったので、この地を修行の場としたとの伝承。 能の「高野物狂」の後半の舞台。この三鈷松の前で主従が運命の再会を果たす。 「花壇上月伝法院。紅葉三宝院よりもなほ深く。雪は奥の院。かれよりもこれよりも。いつも常磐の三鈷の松蔭に立ち寄る春の。風狂じたる物狂ひ/\。あら忘れや。」  根本大塔、高さ50メートル。これはでかい。  三昧堂と手前左の桜は西行桜  金剛峯寺 高野山真言宗の総本山  正門  金剛峯寺の社殿  昭和天皇お手植えの高野槙があった  苅萱堂 先年、九州博多へ行ったときに、「刈萱の関」を訪問。 刈萱道心と石童丸の数奇な運命に感嘆し、はるか高野山に思いを馳せたものである。  ここが刈萱道心と石童丸の修行の場だった  「刈萱道心と石童丸」の物語については、当HPの福岡県太宰府市の「刈萱の関」のページをご覧ください。  堂内には、物語を描いた見事な額が展示されている。とても素晴らしい出来映えで、満足感の高いものがあった。  奥の院に続く道 この「一の橋」から本格的にスタートする。  こんな感じ  大名や有名人の墓があった。これは武田信玄の墓  石田三成の墓  「二の橋」  こんな道が続く  これも  これは「三の橋」。この向こうに奥の院がある。 この橋からは写真撮影禁止。  高野玉川の水行場 |
*********
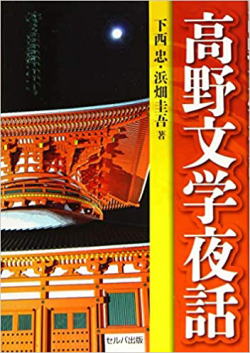
訪問前に読んだ本
六玉川の「高野玉川」と滝口入道のゆかりの「大円院」は
別のページを設けたい。
copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.