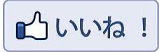「歌枕 歌ことば 辞典」(笠間書院)の説明では、
「大きな堰」(ダムのようなもの)という意味。 平安京ができる前に、渡来人の秦氏によってここに堰が築造され、農業用の灌漑に利用されていたらしい。  現在の堰は昭和26年に京都市が造ったもの。 (中の島から撮影)  これは素晴らしい! 左岸から撮影。  堰から上流はダム湖のようになっていてボート遊びができる。 平安貴族たちもここで舟遊びを楽しんだらしい。 |
西行のうた
| よもすがら嵐の山は風さえて大井のよどに氷をぞしく | 西行 |
| 大井河ゐせぎによどむ水の色に秋ふかくなるほどぞ知らるる | 西行 |
| 大井川君が名残のしたはれて井堰の波のそでにかかれる | 西行 |
| ところで、なぜかしら個人的に「蜻蛉日記」(藤原道綱母)がお気に入りで、とりわけ夫となる藤原兼家の型破りな求婚と、その際の藤原道綱母との歌の遣り取りのくだりは、ある意味コメディタッチで面白い。(?) 歌の問答を繰り返していた二人が、ついに契りを結んだ次の朝、兼家からの歌。 |
| 夕暮の流れくるまを待つほどに涙おほゐの川とこそなれ | 藤原兼家 |
| はじめての夜をともにした今朝の別れの辛さは、ふたたびあなたに 逢える夕暮れを待ちかね、とめどない涙となってあふれています。 (週刊 日本の古典を見る) |
|
これに対し、女
| 思ふことおほゐの川の夕暮は心にもあらずなかれこそすれ | 藤原道綱母 |
| はじめての逢瀬に、もの思いはあとを絶えず、夕暮ともなると われ知らず涙している私になりました。 (週刊 日本の古典を見る) |
|
| こんなかんじでスタートした二人であったが、その後は気位の高い女の嫉妬と恨み言ばかりが続く大変な結婚生活になる。 さて、大堰川と言えば源氏物語で、明石の君が明石から上京してきて住んだ館が「大堰川のわたり」にあった。 光源氏は嵯峨の御堂に法要に行くことにして、大堰に住む明石の君に会いにきた。 かつての夜のことを思い出して感傷的になった光源氏は、預けていた琴を弾き始めたところ、弦の調子も昔のままで、 |
| 契りしに変はらぬ琴の調べにて 絶えぬ心のほどは知りきや | 光源氏 |
と詠むと、女
| 変はらじと契りしことを頼みにて 松の響きに音を添へしかな | 明石の君 |
| と詠み交わした。光源氏は今まで以上に美しくなった明石の君を見て惚れ直したというストーリー。 そんな明石の君が住んでいた「大堰の館」は現在では天竜寺の南側、大堰川のほとり、旅館「らんざん」辺りにあったとされている。  旅館「らんざん」はこの辺りかな? 大堰川は明石の海のようだったと描写されている。 |