| 松原や高洲のこずゑ超るまで月の出しほの更にけるかな | 今川了俊(鹿苑院殿厳島詣記) | |
| 松原の気色よ、高洲に立る松の梢をも浪の越るかと思はるゝまでに 月の出潮の満たらひて、夜の更わたること哉となり 『周防府松崎天神鎮座考』 |
||
| 月の出る頃より満潮に向かう潮の流れを「月の出潮」というらしい。 厳島詣の旅に出た将軍足利義満と随行員たちは、周防国府の南の三田尻に上陸し御旅所を立てた。 そこは松原が広がり 厳島大明神は、当初こちらの松原の地に降臨し、その後に安芸の宮島へ遷っていったと伝わっている。 現在も三田尻の本町通りから新回までを高洲という。昔はこの辺りは全て松原だったという。 ■ 現地訪問 ちょっと失敗した。 三田尻、三田尻と考えていて、到着したのは江戸時代の長州藩の「三田尻御舟倉跡」。今は街中だけど、江戸時代はここまで海が入ってきていたのだ、とか思いながら写真を撮った。    三田尻御舟倉跡 ここに長州藩の船倉があった (山口県防府市三田尻3丁目3?13) 家に帰って整理をしていて、本当に行くべきだったのは、松原厳島神社(防府市華浦2丁目1?3)だったことが判明。将軍足利義満たちが滞在した石上厳島大明神の場所である。周辺には名勝「鞠生松原」の松林が今でも広がっていて、昔ながらの風趣を保っているらしい。 実に残念無念。 |
このページは防府市立防府図書館の防府天満宮縁起集を参考に作成しました
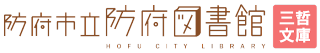
copyright(C)2012 すさまじきもの〜「歌枕」ゆかりの地☆探訪〜 all rights reserved.