瑞厳寺は、
日本三景 松島にある臨済宗の寺院で、
創建は平安時代初期にまで遡り、、
奥州藤原氏の厚い庇護を受け、
仙台伊達家の菩提寺であり、
松尾芭蕉もお参りに訪れたという、
本当に、由緒深いお寺である。
瑞厳寺の入口の前まで行った。

平成の大修理がおこなわれている。

平成の大修理以外に、東日本大震災の津波被害からの復興工事も行われていた。
広大な松林は津波の塩害により大きなダメージを受け、多くの松が枯れて伐採されたとのこと。

中国敦煌の莫高窟のような石窟が掘られていた。
この中で修行をしたのだろう。

いやはや、すごい迫力であった。
実は、ここに来たのは瑞厳寺のお参りが目的ではない。
瑞厳寺に伝わる物語「紅蓮尼」のゆかりの地として訪れたもの。
それは、ええと、・・・
秋田県にかほ市のホームページに詳述されていたので、コピペさせていただいた。
時は元亨(1321〜1324)のこと、象潟の商人、森隼人は西国三十三番観音参りの途中、松島の掃部と道連れとなりました。二人が国へ帰る頃には、森の娘タニと掃部の息子小太郎の縁組の話が出来上がっていました。
森隼人が象潟へ帰ってそのことをタニに伝えたところ、タニはその縁を信じ、まだ見ぬ小太郎に心を引かれていきました。そのときタニは18歳だったといわれ、嫁入りの身支度を調え、はるばる山を越えて松島へ嫁いでいきました。
しかし、松島へ着いてみると、夫となるはずの小太郎はちょっとした病がもとで亡くなっていました。まわりの人たちは、また国に戻ってよき夫に嫁ぐようすすめたのですが、タニは「縁あって約束したからには、小太郎の妻であり掃部家の嫁である。小太郎の供養をしながら、小太郎の両親とともに暮らす」といって、どうしても帰ろうとしませんでした。タニはそれ以後、実の父母に仕える様に婚家の親に孝養をつくしたといわれています。
タニは亡き夫が幼き日に植えたという梅の木に向かって、梅の花を見る小太郎を思って悲しくなってしまうので、
| 移し植えし花の主ははかなくに軒端の梅は咲かずともあれ |
梅の木の主で本来は夫となるべき小太郎もいないのに咲かないでおくれと詠んだところ、翌年はもう花が咲きませんでした。
しかし、咲かなくなってしまうと、また寂しいので、今一度、
| 咲けかしな今は主とながむべし軒端の梅のあらん限りは |
もう一度咲かせてほしいと詠んだところ、また香り高い花をつけるようになったと言います。現在、三聖堂の隣には、仲良く二人の名前を刻んだ石碑があります。
こうして幾年月が過ぎ、老父母の死を見とった後、タニは円福寺(瑞巌寺)に入り、心月紅蓮の名をもらって尼僧となりました。そして生計の為に門前で長方形のせんべいを焼いて商いました(瑞巌寺の観音様に参詣する人たちがお供えした米を粉にして、煎餅を焼いて村の人々に施しをしたことが始まりとも言われています)。松島の人々はこのせんべいを「おこうれん」と呼び、今でもそのせんべいは残っています。おこうれんが長方形だったのは紅蓮尼が和歌を好んだため、短冊の形にしたものといわれています。
紅連は77歳まで生き、人々はこの貞節を末永く称えたのです。
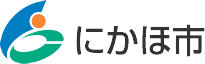 |
これが「軒端の梅」。瑞厳寺の外にあった。
1月に訪問したので、梅の木なのか何なのか分からない。

奥に「比翼塚」がある。
|

